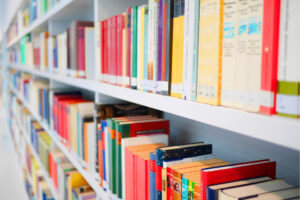私の人格形成に影響を与えた書物と思索 12〔最終回〕
著述業・哲学研究者 〔22〕 碧海純一著『新版 法哲学概論 全訂第一版』に関する論述の最後に、碧海純一先生と私との親交〔お付き合い〕について、簡単に記しておくことにしたい。 私が碧海先生とお付き合いさせていただくように […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 11
著述業・哲学研究者 〔21〕 「正義の諸問題」と題された第八章では、第二次大戦後の倫理学文献において「メタ倫理学」(「メタ法価値論」は、「メタ倫理学」の一分野とみなされている)と呼ばれる学問領域の問題が考察されている。 […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 10
著述業・哲学研究者 〔19〕 『新版 法哲学概論 全訂第一版』の第二章は、「法の概念」となっている。 けれども、ここでの碧海教授の主な意図は、この主題をめぐる在来の論議に自ら参加して、独自の「法」の概念を規定することに […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 9
著述業・哲学研究者 〔17〕 『新版 法哲学概論 全訂第一版』 ―― 知の楽園 ―― 最後に、私は、自分の人格形成、特にその知的な面の形成に大変役立った本として、碧海純一〔あおみじゅんいち〕著『新版 法哲学概論 全訂 […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 8
著述業・哲学研究者 〔15〕 さらに、ここで、以下のことも付け加えておきたい。 それは、教養は、「この世界」が蔵する未知の〔自分が今まで知らなかった〕魅力を、 ―― 「この世界」の対象に対して意味づけを行うことによって […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 7
著述業・哲学研究者 〔13〕 ここで、次のような人生観を考えてみよう。 すなわち、「人生とは、唯一回限りのこの世界への招待であり、人生の目的は、この世界が蔵する(種々の)価値を深く味わうことである。」という人生観であ […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 6
著述業・哲学研究者 〔11〕 私は、上記において、「教養の持つ最大の意義」は「私たちの見ている世界を変えてしまう」ことにある、と述べた。そして、そのことを説明するために、教養は知識の一種であることを考え、「英文読解」や […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 5
著述業・哲学研究者 〔10〕 小説『ドリアン・グレイの肖像』や戯曲『サロメ』、童話「幸福な王子」などの作品で知られるイギリスの作家オスカー・ワイルド(1854~1900年)は、「虚言の衰退〔“The Decay of […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 4
著述業・哲学研究者 〔7〕 まず、「英文読解」を例に出してみたい。(「英文読解」と言っても、難しい英文を問題にするつもりはない。易しい英文で十分である。) 今、AとBという二人の人間がいるとする。 Aは英語がきわめ […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 3
著述業・哲学研究者 〔5〕 ここで、「数学を学ぶことの意義」について、私の思うところを記しておきたいと思う。 私たちは、一般に、中学一年生で(xを未知数とする)一元一次方程式を学び、高校生になってから対数関数や三角関数 […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 2
著述業・哲学研究者 〔3〕 私は、上記において、小学校四年生の国語の教科書に載っていた「しあわせの島」という物語に関して、自分の意見を述べた。「しあわせの島」の内容は、直接私の人生観になったわけではなく、それを批判して […]
私の人格形成に影響を与えた書物と思索 1
著述業・哲学研究者 1958年 埼玉県に生まれる。 慶應義塾大学経済学部卒 現 在 著述業 哲学研究者日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員(日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の […]