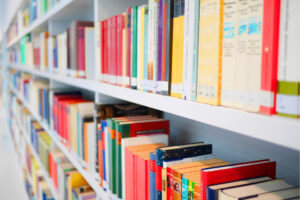私の人格形成に影響を与えた書物と思索 2
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔3〕 私は、上記において、小学校四年生の国語の教科書に載っていた「しあわせの島」という物語に関して、自分の意見を述べた。「しあわせの島」の内容は、直接私の人生観になったわけではなく、それを批判して得られた結果としての内容が、私の人生観の一部になったのであった。
そして、その内容は、ドイツの文豪ゲーテ(1749~1832年)の思想に接近する。それは、ゲーテの思想そのものと言ってもよいかもしれない。
ゲーテは、(1)「我々が旅行をするのは、着くためではなく、旅行をするためである。」と述べているが、その意図するところは、結果ばかり執着するのではなく、その過程を十分に楽しみ味わわなければならない、ということであろう。
手塚富雄氏(1903~1983年、ドイツ文学者、元東京大学名誉教授、元日本学士院会員、当時の「ゲーテ研究」の第一人者)は、名著『いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ』(講談社現代新書、1968年)において、直前に引用したゲーテの言葉のすぐ前で、「かれ[ゲーテ]はただ結果を生むためにがめつく仕事をするというのではなくて、仕事そのものの過程を楽しんだということである。この気持ちがあるから息切れがせず、結果として大きいことをすることができたのである。……『はたらく』ということのほんとうの秘訣はそういうところにあるだろう。」と述べている。私も全く同感である。
私は、先に、自分は哲学の研究に携わっている身であり、「哲学の未解決の問題が解ける」ことには非常に大きな価値があるが、「その問題を解こうと全力を傾けて懸命に考えている」ことに、人生におけるそれ以上の価値があると考えている、と述べた。そして、私は、同時に、その問題を解こうと全力を傾けて懸命に考えている時に、「考えていること自体を楽しむ」ことがとても大切であると考えている。このことは、是非ここに記しておきたいと思う。
前記『いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ』は私が二十歳を過ぎてから読んだ本であるが、人生観を考えるに際して大変有意義な本で、私にとって座右の書の一つである。
私は、自分の人生観を形成する上で、自分自身で思索した部分も少なくないが、この本から学んだ部分も小さくない。この本は、手塚氏がゲーテの知恵の最高のものと考える「ゲーテの言葉」を選んで来て、その言葉に手塚氏が受け答えをし、そこに一種の両者の内面の交渉が浮かび上がるようにした内容となっている。
本書には、私の好きな言葉、印象に深く残っている言葉として、他に、
(2)生きているあいだは、いきいきとしていなさい。(1818年12月作「仮装行列」中のメフィストの言)
(3)意欲と愛は偉大な行為にみちびく両翼である。(『イフィゲーニエ』)
(4)誠実な友よ、何を信じたらいいか、言ってあげよう。生を信じなさい。生の教えは雄弁家や書物よりはるかによい。(詩「四季」)
(5)永遠なる女性的なるもの、われらを高みへ引き行く。(全『ファウスト』の終わりの言葉)
などがある。
(2)手塚氏は、本書において、「生きているあいだは、いきいきとしていなさい。」について、「昼のあいだは、はたらきなさい。」(ボアスレーあての手紙)とともに、「もしゲーテの人生観と生き方を、いちばん手短に平易に言い表しているものを選ぶとしたら、この二つにまさるものはあるまい。」と述べる。「簡潔で、理屈がないから、それだけ活力が大きい。ゲーテのような生きることの天才でなければ、とてもこうは言えない。ときどきこういういぶきを浴びるのはわれわれの薬になる。」と言う。本書のタイトルが『いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ』となっているのも、上述の趣旨によるものであろうと思う。
(3)「意欲と愛は偉大な行為にみちびく両翼である。」については、手塚氏は、「ある仕事にたいする愛と、それをしたいという気持ち[意欲=Lust(独語)]、それが根本のことである。」と言い、そして「またそれさえ失わないでいれば、われわれにも大きい行為をする可能性は残されよう。」と述べる。
(4)「誠実な友よ、何を信じたらいいか、言ってあげよう。生を信じなさい。生の教えは雄弁家や書物よりはるかによい。」について、手塚氏は、「ここでまた、ゲーテの生き方の核心が言われた。……ゲーテは勇気をもって、生を信じ、生の教えに耳を傾けたのである。」と言っている。そして、さらに、手塚氏は、「これと同じ根から出たゲーテのことばをあげておこう。」として、以下の二つの言葉を記している。
わたしと同じように生活を愛そうと試みたまえ。(『ツァーメ・クセーニエン』)
いつか死ぬという事実にさからってなんになる。そのために君は生をにがくするだけだ。(「エピグラム風」)
世に、世界最高の厭世詩人として知られるイタリアのG・レオパルディ(1798~1837年)や夭折した中唐の鬼才詩人の李賀(791~817年)、19世紀ドイツの厭世的哲学者・思想家のショーペンハウアー(1788~1860年)といったペシミスト〔厭世主義者〕たちがいるが、それに対して、ゲーテは、これらの言葉から、厭世主義とは正反対に、「生」を積極的に肯定していることがわかる。
(5)「永遠なる女性的なるもの、われらを高みへ引き行く。」は、先にも記したように、『ファウスト』第二部の終幕 ―― ファウストの魂が救い取られる壮麗な場面 ―― の最後、すなわち全『ファウスト』の終わりの言葉である。
この言葉について、手塚氏は以下のように言う。
……けっきょく男性の原理と女性の原理とはちがうのであって、それが愛によって結ばれるとき、人間性は美しく開花するということを思わずにはいられない。男性の原理とは、行動である。強いエネルギーでどこまでも突進してゆく。行動だけが一切であるように。したがって、強力な行動人であることによって、そのまま悪魔にもなりうるのである。……
それにたいして女性の原理は、行動のエネルギーはもたない。もっても少ない。しかし男性に代表される行動を、悪魔化しないように、よりよいものに、より美しいものに高めることはできる。それは愛による願いによってである。どんなに弱いように見えても、それがけっきょくは男性の原理を動かし、引き上げずにはいないのである。男性の原理は必ずそれについて行く。ついて行くことが喜びだからである。女性の原理にとっては、引き上げることが喜びなのである。この二つ[男性の原理と女性の原理]が結びつきを求めることが、「エロス」という語の最高の意味であろう。……
われわれは「永遠なる女性的なるもの」に思いをひそめ、それを敬うことを学ばなくてはならないと思う。
手塚氏は、このように述べる。
現代は、個〔個性〕を重んじ、「男らしさ」や「女らしさ」に否定的な風潮の時代であるから、手塚氏の見解に賛同しない方も少なくないと思われる。私は、それはそれでよいと思う。ただ、私自身としては、男性にも女性にもいろいろな性格の人がいることは事実であるが、大雑把に言えば、現代でも男性の原理・女性の原理について、手塚氏の言うような傾向があると言えるのではないかと思っている。「性」というのは、最も基本的な生物学的相違に根差して成立しているものである、と言うことができる。
(因みに、ゲーテ『ファウスト』の手塚富雄訳は、森鴎外〔森林太郎〕訳以来の名訳とされている。)
以上、『いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ』の内容についてほんの一部を引用したが、私は、基本的に、ゲーテの人生観が好きである。彼は、現実を柔軟な心でありのまま受け止め、その上で現実に溺れず、理想を持ってそれに対処していった人間であった。私は、本書は、私の人格形成において、少なからぬ役割を果たしていると考えている。
なお、手塚富雄氏には、『人類の知的遺産45 ゲーテ』(講談社、1982年)という本もある。「人類の知的遺産シリーズ」は、「この1冊で過去の知者・賢者の生涯、思想、著作のすべてがわかる」ということをコンセプトにした全80巻のシリーズ本であるが、ゲーテを扱った『人類の知的遺産45 ゲーテ』も、手塚氏によってゲーテの生涯、思想、著作が要領を得て十分にわかるように配慮がなされており、大変有益な本である。
私は、同じ著者〔手塚富雄氏〕の『いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ』と『人類の知的遺産45 ゲーテ』を併せ読むことによって、ゲーテの思想についての理解が一層深まるとともに、自分の人生観を形成していく上で、大いに資するものになると考えている。
〔4〕 小学四年生の時に読んだ「しあわせの島」との関連で、手塚富雄氏の『いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ』に言及して来たが、また時間を小学校の時に戻したいと思う。
私が小学五年生になる春休み頃だったと思うが、父が『力の算数5000題』(教学研究社)という小学校高学年用の算数の参考書を買って来てくれた。私はその参考書を買ってくれたことに対して父にお礼は言ったものの、その本を勉強机の上の本立てに置いたまま、しばらく読むことはなかった。
五年生の夏休みの終わり頃になって、何となくパラパラとその本のページをめくって見てみた。
最初その参考書のどこの部分を見たのか忘れてしまったが、しばらくして昔からある算数の文章問題〔文章題〕に興味を持つようになった。すなわち、植木算、平均算、相当算、旅人算、時計算、通過算、流水算、年齢算、鶴亀算、方陣算などである。たしか、全部で20種類程の文章問題が載っていたと思う。
その本は、各文章題ごとに(例えば、通過算なら通過算について)、その文章題についての考え方や解き方がわかりやすく記されており、その後、「C実力問題」と「D応用問題」として、それぞれに10~15題程度のその文章題に関する問題が載っていた。
初めのうちは、「C実力問題」や「D応用問題」は解けないことも多かったが、解いて本の「解答」を見て答えが合っていると子どもながらとても嬉しかった。
そのうち、問題を解くことが好きになってきた。また、難しい問題を考えること自体も楽しいと感じるようになった。1つの問題を1時間位あるいは2時間位考えることもあったが、そのことが苦痛であるとはあまり思わなかった。今思うと、それは、私が性格的に物事に対する「執着力」が普通の人より強いせいであると思われる。
私は、その参考書によって、「もの〔問題〕を考えることの楽しさ」を知った。また、自分の「思考力」も、その参考書によって、以前と比べてかなり向上したと思う。(私は、小学六年生の夏頃には、『力の算数5000題』は、同じ問題を二、三回解いてしまったので、親に頼んで『応用自在』(学習研究社)という別の小学校高学年用の算数の参考書を買ってもらった。)
現在、私は哲学に携わっている身であるが、私は「哲学の生命は自ら考えることにある」と思っている。前述の参考書によって「もの〔問題〕を考えることの楽しさ」を学んだことは、現在の研究にも少なからずプラスの影響を及ぼしていると思っている。
また、先に記したように、私は物事に対する「執着力」が普通の人より強い性格であると思っているが、その性格も哲学には有利に働いていると思われる。
哲学の問題はどれもきわめて難しく、そう簡単に解けるようなものではない。とりわけ哲学の根本問題、基本問題に至っては、一般に、一生かかっても解けないのが普通であると考えられている。
戦後の日本の哲学界を代表する哲学者の一人である大森荘蔵氏(1921~1997年、元東京大学名誉教授)は、彼のある著書の「序」において、次のように述べている。
それら[本書に収録した十三篇の論文]はある主題のまわりをメリーゴーラウンドのようにめぐっている。それは第一章から出発し終章に終って旅をおえるといった直線的旅行ではなく、いくらかでも輪を狭めることを望みながらの堂々巡りの旅だといえよう。ヴィトゲンシュタインは哲学をハエ取器[ハエ取り壺]にかかったハエにたとえたが、もしそうだとすれば哲学の行路の軌跡はそのようである以外にはあるまい。さらに、ハエが脱出し哲学が完結するといった事態を想像できる哲学者がいるだろうか。完結し終了した哲学史なるものを考えることができるだろうか。(大森荘蔵著『言語・知覚・世界』、岩波書店、1971年 の「序」ⅲ頁。)
上の大森荘蔵教授の著書からの引用において、「ハエがハエ取器[ハエ取り壺]から脱出する」というのは、「苦闘したあげく哲学の問題を解決する」ということの比喩である。大森教授は、哲学の問題の難しさについて、以上のように述べるのである。
このような次第であるから、物事に対する「執着力」が強くなくすぐに飽きてしまったり諦めてしまうような性格であったならば、たとえどんなにIQ〔知能指数〕が高くても、哲学には不向きであると思われる。自分の物事に対する「執着力」の強さは、前述の算数の文章題を考える際にも多少なりとも表れていたと思われるが、偶々自分が、物事に対する「執着力」が強い性格であったことは、先にも述べたように、現在の研究において少なからず幸いしているように思われる。
次回の掲載は12月6日の予定です。
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。