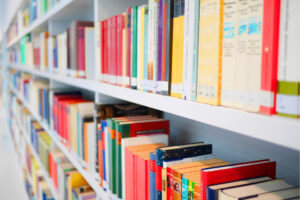私の人格形成に影響を与えた書物と思索 6
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔11〕 私は、上記において、「教養の持つ最大の意義」は「私たちの見ている世界を変えてしまう」ことにある、と述べた。そして、そのことを説明するために、教養は知識の一種であることを考え、「英文読解」や「掛け時計」を例に挙げて、「知識」が「私たちの見ている世界を変えてしまう」ことを示した。
けれども、「教養」は知識(の一種)ではあるが、私たちが日常生活を営むのに必要な最低限度の知識は、一般に「教養」とは言わないであろう。「教養」とは、私たちが日常生活を営むのに必要な最低限度の知識以上のもの〔知識〕である、と言うことができると思われる。したがって、その意味では、上述した「掛け時計」の例は、「知識」が「私たちの見ている世界を変えてしまう」例であるとは言えるが、「教養」が「私たちの見ている世界を変えてしまう」例と言うことはできないと思われる。「掛け時計」についての知識は、私たちが日常生活を営むのに必要な最低限度の知識とみなしうるためである。
しかし、「教養」も、「知識」の一種として、 ―― 他の多くの「知識」の場合と同様に、対象に対して「意味づけ」を行うことによって ―― 「私たちの見ている世界を変えてしまう」働きがあると言うことができると考えられる。
ところで、例えば世界の180か国以上の国々の人口をむやみに覚える〔暗記する〕ことは、たしかに私たちが日常生活を営むのに必要な最低限度の知識以上のもの〔知識〕を有することであるが、それによって ―― 世界における対象に対して「意味づけ」を行い ―― 「自分の見ている世界を変えてしまう」ことにはほとんどならないであろうと思われる。この点で、世界の180か国以上の国々の人口をむやみに覚える〔暗記する〕ことは、露風の「去りゆく五月の詩」を味わいその詩の知識を有することとは、異なっていると言えよう。
「教養」は、私たちが日常生活を営むのに必要な最低限度の知識以上のもの〔知識〕であるとともに、対象に対して「意味づけ」を行うことによって「私たちの見ている世界を変えてしまう」ような知識である、と言うことができると考えられる。
すなわち、「教養」は、単に知識が多いか少ないかという(すなわち、単に物知りかどうかという)そのようなレヴェルのものではなくて、むしろ知識が「私たちの見ている世界を変えてしまう」ということに、その本質的な意義があると考えられる。
もっとも、「教養」をこのように定義するならば、定義上、「教養」が「私たちの見ている世界を変えてしまう」ことは当然のことになると言えよう。
けれども、私は、「教養」については、上記のように定義するのが適当なのではないかと思っている次第である。
〔12〕 ここで、私は、無知のため本当は価値のないものを賞賛することよりも、無知のため真に価値のあるものの価値がわからない(したがって、そのような価値のあるものを賞賛しない)ことのほうが、はるかに多いと考えられる、ということを述べておきたいと思う。
朱牟田夏雄(元東京大学名誉教授)著『英文をいかに読むか』(文建書房、1959年)(全三編より成る)の第一編「総論」の中に、次のような英文解釈の問題がある。
(この本は、英文解釈の参考書であり、原則として、初めに各英語の文章が載っており、その後、その英文についての解説が述べられていて、締め括りに、その英文の和訳が記されている。ここでは、上に記した英文解釈の問題の和訳(中間部分を省略した抄訳)を、本書の和訳〔朱牟田氏の訳〕の言葉を若干改変して記すことにする。)
私たちは、実際、賞賛は無知から生まれると聞かされることが珍しくない。しかし、これ以上嘘の言葉は古来全くないし、これ以上有害な言葉もめったにない。……(中略)……ところが、実際は、もっと十分に見る目があるならばありふれたものであるとわかるもの、したがってそのように賞賛する値打ちのないもの、そういうものを私たちが無知のために賞賛する場合に比べて、本当に賞賛に値するものを無知のために賞賛しない場合の方が、百倍いや千倍も多いのである。
私は、(百倍や千倍という具体的な数値は別として)上記の引用文の内容に基本的に賛同する。
そして、引用した上の文章において、「無知」を「教養がないこと」に置き換えるならば、教養がないために真に価値あるものの価値がわからないことは、非常に多いと思われる。
教養がないために、「対象」(例えば、「去りゆく五月の詩」の例で言えば、「五月の終わり頃の自然」)に十分な「意味づけ」ができないのである。すなわち、教養がないために、対象の有する「認識意味」〔「認識的な意味」〕を、十分に完全に近い程度に確定できないのである。
もし、十分な教養があるならば、対象の有する「認識意味」を十分に完全に近い程度に確定できて、その「認識意味」に基づいて生ずる「情緒意味」(すなわち、「情感」)が、「よい」という「情緒意味」 ―― すなわち、対象への志向性〔その対象に好感を持って、その対象に向かおう(接近しよう)とする心の状態〕を与えるようなすべての「情緒意味」・の集合 ―― に属する(この場合には、その対象に対して「よい」という価値判断が為されることになる)にもかかわらず、
教養がないために、対象の有する「認識意味」を十分に完全に近い程度には確定できず(場合によっては、完全から程遠い程度にしか確定できないで)、その「認識意味」に基づいて生ずる「情緒意味」が、「よい」という「情緒意味」に属さない(この場合には、その対象に対して「よい」という価値判断が為されない)のである。
(すぐ上の段落で述べたことをより平易な表現で言うならば、)教養が十分にあれば、ある対象について、それを「よい」と判断できるが、教養がないと、それを「よい」と判断できないことが、(非常にしばしば)起こるということである。
教養の「ある」、「なし」は、認識的な面において、「私たちの見ている世界を変えてしまう」だけでなく、 ―― そのことを通じて ―― 情緒的な面において、「対象についての『よし悪し』の価値判断まで変えてしまう」のである。先に挙げた三木露風の「去りゆく五月の詩」は、「この詩の鑑賞」(教養)によって「五月の終わり頃の自然」(対象)が今までになく魅力的に感じられるようになることから、むしろこの例〔対象についての「よし悪し」の価値判断を変えてしまう例〕であると言った方がより適切であると思われる。
次回の掲載は、2025年4月21日の予定です。
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。