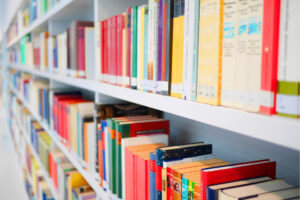私の人格形成に影響を与えた書物と思索 7
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔13〕 ここで、次のような人生観を考えてみよう。
すなわち、「人生とは、唯一回限りのこの世界への招待であり、人生の目的は、この世界が蔵する(種々の)価値を深く味わうことである。」という人生観である。
これは、私が四十年来採っている人生観である。
人生観というのは主観の混入を避けることが困難であり、また、それに対して、学問の生命はその客観性〔客観的妥当性〕にあると考えられるため、人生観というのは学問の対象とはなりにくいと考えられる。けれども、上記の人生観は、私なりにできるだけ客観的妥当性を有する内容となるように形成したものである。
この人生観については、言うべきこと〔註釈すべきこと〕がたくさんある。しかし、この人生観について十分詳細にわかりやすく解説することは紙幅の点からも無理であるので、ここでは次の点だけ述べておきたい。
それは、「この世界において人生を生きる」ことと、「東京ディズニーランドに行って一日(ないし二日)過ごす」ことは、ある本質的な意味において同様である、と私が考えているということである。
もちろん、「この世界において人生を生きる」ことと、「東京ディズニーランドに行って一日(ないし二日)過ごす」こととでは、そのスケールにおいて、月とスッポン程の大きな違いがある。しかし、前述したとおり、ある本質的な意味においては同様である、と思われるのである。
私たちが東京ディズニーランドに行った時、そこでのレジャーのメインとして、自分の気に入ったアトラクションに乗ったりするであろう。そして、午後の1時頃、園内でパレードが行われるとすれば、もしそれが観たいと思うならば、それを観ることであろう。
また、自分の乗ったり見たりするアトラクションとアトラクションの合い間に、なんとはなしに建物の裏の細い道を歩いていた時に、道端に一輪の小さな可憐な花が咲いているのを見つけ、その花に不思議な魅力を感じることもあるかもしれない。
さらに、夕方には、レストランでアイスティーを飲みながらくつろいでいる時、ふと窓の外を見たら、木の葉が一枚そよ風に吹かれて打ちふるえていたとしたら、次のような言葉が脳裏に浮かぶかもしれない。
打ちふるえる一枚の木の葉によって、
極度の絶望からわずかに分け隔てられた極度の至福、
それが人生ではなかろうか。
(この言葉は、実は、19世紀のフランスの文芸批評家、サント=ブーヴ(1804~1869年)の言葉である。イギリスの作家、W・サマセット・モーム(1874~1965年)は、1921年に『木の葉のそよぎ』〔The Trembling of a Leaf〕という短編集を出版した時、その題名を上記のサント=ブーヴの言葉から取り、その本の巻頭にこの言葉を引用している。)
愛児を失った親というのは、疑いもなく人生最大の不幸のうちにあると言えようが、それでも、もしかしたら夕方そよ風に打ちふるえる一枚の木の葉を見て不思議な幸福感に包まれて、上のサント=ブーヴの言葉のような思いを持つことがあるかもしれない。
このようにして東京ディズニーランドでの一日は暮れてゆく。そして、乗りたいものや見たいものも一応乗ったり見たりしたし、お店〔shop〕で買いたい物も買ったし、もうすぐ夜の9時になるからそろそろ帰ろうか、ということになる。
東京ディズニーランドにおける「価値」は一応満喫した、ということである。
「人生とは、唯一回限りのこの世界への招待である。」という言葉は、おそらく読者の方に納得していただけるのではないかと思う。実は、この言葉に関連して述べておきたいことはたくさんあるのだが、書きだすとかなり長くなるので、すべて割愛することにする。
「人生」が「唯一回限りのこの世界への招待」であるならば、「人生の目的」を「せっかく訪れたこの世界〔例えば、85歳まで生きるとするならば、85年間程滞在するこの世界〕に在る『価値』を、できるだけ多く深く味わおうとすること」であると考えることは、「自然で理に適った見解」である、と私には思われる。ちょうど、東京ディズニーランドを訪れた時、そこにおける「価値」を満喫することが、東京ディズニーランドを訪れた「目的」であるように。
「人生の目的」も「東京ディズニーランドを訪れる目的」も、訪れた世界や場所における(あるいは、訪れた世界や場所が蔵する)「価値」をできるだけ多く深く味わうことにある、と考えられるという点において、「この世界において人生を生きる」ことと、「東京ディズニーランドに行って一日(ないし二日)過ごす」ことは、ある本質的な意味において同様であると、私は考えるのである。それが、私が前述した「『この世界において人生を生きること』と、『東京ディズニーランドに行って一日(ないし二日)過ごすこと』は、ある本質的な意味において同様である」という見解についての「説明」である。
〔14〕 ここで、さらに、先程私が述べた「教養がないために真に価値のあるものの価値がわからないことは、非常に多いと思われる。」という見解を思い出していただきたい。
「人生の目的は、この世界が蔵する(種々の)価値を深く味わうことである」とするならば、この世界が蔵する(種々の)価値に対して盲目であることは、大変残念であり、もったいないことである、と言わねばならない。この世界が蔵する(種々の)価値に対して盲目であっては、「人生の目的」をほとんど達成することができないと考えられるためである。
そして、前述した如く、教養がないためにこの世界が蔵する(種々の)価値に対して盲目である〔この世界が蔵する(種々の)価値がわからない〕ことは、非常に多いのである。
したがって、「教養がない」ということは、前述した「人生の目的」を達成することにおいて、ほとんど致命的ともなりかねない、と考えられるのである。
ここに、「人生における教養の持つ決定的な重要性」がある、と言い得る。私は、この意味において、「教養」は「人生における大変貴重な一生の財産」である、と考えている。
私は、上記において、「教養の持つ最大の意義」について、「私たちの見ている世界を変えてしまう」ことである、と記した。すなわち、「教養」が「ある」のと「ない」のでは、「見ている世界が違う」のである。そして、それは、(先程の「掛け時計」についての、普通の〔健常な〕大人と二歳になったばかりの幼児の認識の相違が、典型的に示すように)「住んでいる世界が違う」とさえ言い得ると思われる。
けれども、「教養の持つ最大の意義」は、そのこと〔私たちの見ている世界を変えてしまうこと〕を通して、「私たちの人生を飛躍的に豊かなものにする」ことである、とも言い得るのである。「教養」が「ある」のと「ない」のとでは、対象についての「よし悪し」の価値判断でさえも変わってしまうためであり、先の『英文をいかに読むか』からの引用が示すように、教養があるために対象の有する真の「よさ」がわかり、それをこよなく愛し味わうことができることが、大変多いからである。
私は、以上に記して来た「私の思索」に基づいて、「人生において、教養は非常に大切なものである」と述べたいのである。
次回の掲載は、2025年5月23日の予定です。
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。