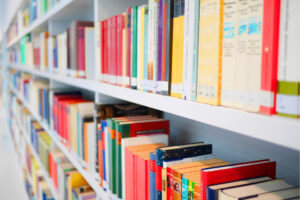私の人格形成に影響を与えた書物と思索 9
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔17〕 『新版 法哲学概論 全訂第一版』 ―― 知の楽園 ――
最後に、私は、自分の人格形成、特にその知的な面の形成に大変役立った本として、碧海純一〔あおみじゅんいち〕著『新版 法哲学概論 全訂第一版』(弘文堂、1973年)を挙げたい。
碧海純一氏(1924~2013年)は、元東京大学名誉教授(元同大学法学部教授、専攻:法哲学)で、法哲学・社会哲学国際学会連合名誉会長でもあられた学者である。
上記『新版 法哲学概論 全訂第一版』は、その後改訂され『新版 法哲学概論 全訂第二版』(弘文堂、1989年)として出版され、さらに現在では『新版 法哲学概論 全訂第二版補正版』(弘文堂、2000年)となって刊行されているが(もしかしたら、品切れになっているかもしれない)、以下では、私が最初に読んだ『新版 法哲学概論 全訂第一版』に基づいて論述したいと思う。(私は碧海教授の正規の門下生ではないが、碧海教授は私が最も大きな学恩を賜った方であるので、以下「碧海(純一)先生」と呼ばせていただくこともある。)
この本は第一級の「法哲学の概説書」であるとともに、「思考方法論」等を学ぶための「(ハイレヴェルの)教養書」としても大変すぐれた著書である。
この著書は、たしかに「法哲学」の概説書なのであるが、「法哲学のテーマ」を題材として、「学問論」をその一部として含む「思考方法論」について教授し、読者の「思考力」を飛躍的に向上させるのに大いに資するような書物なのである。
私は四十年以上前にこの本を読んだ時、その文章の類い稀な澄明さとともに、その内容のすばらしさに多大の感銘を受けた。そのため、私は友人にも三人程に、「教養書」として、この本を薦めて買わせたことがあった。もっとも、彼らが本当にこの本を読んだかどうかは、わからない。
この本には、クワインやT・クーンなどの名前およびその学説について触れられていないという憾みが、たしかにあるかもしれない。しかし、その点を考慮に入れたとしても、本書は、「学問論」をその一部として含む「思考方法論」を学ぶのに、そして自らの「思考力」を強化・向上させるのに、非常に有益な本である、と私は考えている。
私は、十代後半や二十代前半の若い方々〔大学生位の年齢の方々〕を初めとするすべての方々に、「法哲学のテーマ」を題材にした・「思考方法論」を学び思考力を飛躍的に向上させるための大変すぐれた「教養書」として、本書が読まれることを、強く希望する次第である。
私が哲学研究を自分のライフワークにしようと本格的に考えるようになったのは、二十代の前半にこの本を読んだことがきっかけであった。その意味でも、私はこの名著からは極めて大きな影響を受けていると言える。
碧海先生のこの本を読んだ後、私は同先生の他の本も読みたくなり、『合理主義の復権』(木鐸社、再増補版、1981年)、『法哲学論集』(木鐸社、1981年)、『法と言語』(日本評論社、1965年)などの著書を精読した。これらの碧海先生の著書を拝読することによって、私は、少なくとも当時の(「現在においても」と言ってもよいかもしれない)日本の法哲学界において最高水準の内容を有する「碧海法哲学」の概要を中心とする、非常に多くの貴重な知識を学ぶことができた。
碧海先生の著書を読んで私が感じたことのうち、特筆すべきこととして、書かれる文章がこの上なく明晰でわかりやすいことと、扱われるテーマがどれも些末的なものではなく、非常に興味深いものであるということが、挙げられる。同先生が1975年から十年間、当時の文化庁の国語審議会の委員をされていたことも、上記のことと無縁ではなかろうと思われる。
碧海先生の文章は、上述のように極めて〔この上なく〕明晰でわかりやすいとともに、独特の高い知的エートスが感じられる文章であるので、碧海先生のお名前を隠して(すなわち、執筆者が誰であるかを知らないで)その文章を読んだとしても、「これは、碧海先生が書かれた文章である」とわかる程なのである。
〔18〕 さて、最初に挙げた『新版 法哲学概論 全訂第一版』に戻りたいと思う。
この本は、全八章より成っている。
具体的に記すならば、第一章「序論」、第二章「法の概念」、第三章「法の社会的機能」、第四章「記号の意味と解釈」、第五章「法の適用と解釈」、第六章「法解釈学の性格と任務」、第七章「法の経験科学」、第八章「正義の諸問題」である。
(最新版の『新版 法哲学概論 全訂第二版補正版』では、このうち第五章が(「法哲学概論」というよりも)「法学概論」的なものであるという理由で全部削除され、第八章に「正義論の歴史」が、そして第九章に「現代の正義論」が、それぞれ置かれている。第八章と第九章の執筆者は碧海教授ではなく、小林公〔いさお〕教授と森村進教授である。(因みに、『全訂第二版補正版』の参考文献欄において、文献の追加の作業を行ったのも、碧海教授ではなくて、このお二人であると思われる。)また、『全訂第一版』の第三章は、『全訂第二版補正版』では第三章「社会統合と言語」とタイトルが改められるとともに、論述内容も刷新されている。さらに、『全訂第一版』の第六章は『全訂第二版補正版』の第五章に、前者の第七章は後者の第六章に、前者の第八章は「正義論の基礎 ―― メタ倫理学の諸問題」とタイトルが改められて後者の第七章に、それぞれ移っている。)
以下において、私は、自分が最初に読んだ『全訂第一版』の内容の要点を、各章ごとに記したいと思う。
まず、第一章「序論」においては、特に目を惹くのは、「本書における著者の基本的視点」(すなわち、『全訂第一版』における碧海教授の基本的視点。因みに、これは、『全訂第二版補正版』でも基本的に変わっていない)という項目である。そこには、碧海先生の、この著書における基本的立場がどのようなものであるかが、明記されている。それは、碧海先生の「学問観」でもある。そして、それを熟読することは、私たちが「思考方法論」について学ぶ上で、大いに有益である。
この著書において、「本書における著者の基本的視点」として、以下の六つの点が挙げられている。
基本的視点の(1)として、「学問の生命」が「真理」にある、ということが述べられている。そして、このような「学問における真理至上主義」は、今日においてさえ、むしろ少数説だと言っても過言ではない、とされる。
次に、基本的視点の(2)として、「客観性の追求」を挙げている。
ここで、「客観性」とは、「事実と論理とに基づくところの、即物的でかつ間主観的〔インターサブジェクティヴ〕な論議・批判の可能性」であり、それを担保するのは、権力に阿〔おも〕ねらず、事大主義に毒されず、いかなるタブーをも怖れないところの学問的態度であり、これを換言するならば、「知的廉直〔れんちょく〕」ということになる。(「廉直」とは、「心がきれいで私欲がなく、曲がった事は少しもしないこと」である。)
(3)として、「修正主義的認識論」を挙げている。
人間は、学問において、誤りを犯しやすい(「可謬〔かびゅう〕主義」)が、その誤りを修正していくことが大切である。
この可謬主義・修正主義的認識論は、人間理性の自己矯正力への信頼を通じて、人間の認識能力への基本的オプティミズム〔楽天主義〕と結び付いた立場である。
(4)として、「『合理論』と経験論との結合」が挙げられている。
認識における「理性」または「想像力」の能動的役割は重視しなければならないが、一方で、経験的事実による実在認識のコントロールも不可欠である。このような見解は、(ヨーロッパ)大陸型「合理論」とイギリス型経験論との興味ある結合形態を示している。
(5)には、「言語分析の重視」が挙げられている。
認識のための枠組〔フレームワーク〕としての言語の重要性を考えるならば、厳密な言語分析こそ実在認識のための最も重要な手続きの一つであり、これを等閑視して実在の把握を急ぐ者は、結局、言語の問題と事物の問題との不断の混淆に翻弄され、所期の目的を果たすことができない。
しかし、言語分析は、実在認識のための不可欠の手続きの一つに過ぎず、「言語分析が哲学のすべてである」という極端な分析至上主義は哲学の些末化に通ずる、という見解が、述べられている。
(6)としては、「合理主義の限界とその倫理的前提との自覚」を挙げている。
碧海教授の基本的な学問的立場は「批判的合理主義」と言ってよいが、その立場によれば、合理的・「科学」的方法のみによって倫理的価値判断の問題は解決できないとする。
また、批判的合理主義者は、自らの立場がそれ自体一つの基本的な倫理的決断に ―― すなわち、「理性への帰依」に、換言すれば、合理的・間主観的な議論によって諸問題の解決をめざす姿勢の主体的な選択に ―― 依存するものであること、並びに、この決断そのものの妥当性は、科学的な証明を越えたものであることを、率直に認容する。
以上の(1)~(6)が、第一章「序論」における「本書における著者の基本的視点」である。
私自身としては、ここでの碧海教授の見解と異なる意見を有する点も全くないわけではないが、そのことを考慮しても、私は、この第一章「序論」の「本書における著者の基本的視点」は、先にも述べたように、「学問論」を含む「思考方法論」を学ぶ上で、大変有益であると考えている。
次回の掲載は、2025年7月18日の予定です。
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。