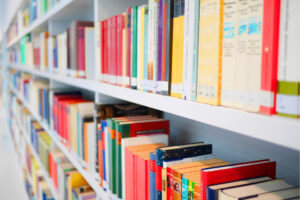私の人格形成に影響を与えた書物と思索 10
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔19〕 『新版 法哲学概論 全訂第一版』の第二章は、「法の概念」となっている。
けれども、ここでの碧海教授の主な意図は、この主題をめぐる在来の論議に自ら参加して、独自の「法」の概念を規定することにあるのではない。
本章の論述では、諸科学、特に人文・社会諸科学、における概念規定の論理学的・認識論的な基本問題を、法哲学の枠を越えて一般的に問い直し、概念規定という論理学上の操作の性格を解明することに重点が置かれている。
「定義」の問題(すなわち、概念規定の問題)を正しく考察するためには、まず、定義と定義と一見類似する二種類の文、すなわち、(C・G・ヘンペルの言う)「経験分析」と(同)「意味分析」との混同を犯さぬことが必要不可欠である、と碧海教授は言う。
例えば、「人間は理性的動物である」と言う場合、この文が(1)「『人間』という言葉を『理性的動物』という言葉と同義に用いることにしよう」という決定(定義)なのか、(2)「『人間』という言葉で指示されている対象は、動物であってかつ理性的である」という対象の性質についての主張(経験分析)なのか、それとも、(3)「『人間』という言葉と『理性的動物』という言葉とは同義に用いられている」という言葉の用法についての主張(意味分析)なのかは、必ずしもはっきりしない。この一番大切な区別をはっきりせずにいくら議論してみても、明確な解答が出て来ないのはむしろ当然である。
今まで哲学者や社会科学者はしばしばこのような問題設定の局面での明確な分析と自覚を欠いたまま論議を重ねて来たのであり、法哲学者も決して例外ではなかった。「法とは何ぞや」、「法の本質いかん」、「悪法は法なりや」、などの問題が救い難い程の混迷状態を引き起こしたのは、法についての私たちの認識が不完全であったというより以上に、最初の問題提起が十分に一義的でなかったからなのである。
もし、出発点において、問われているものが定義なのか、経験分析なのか、それとも意味分析なのかが明示され、それに応じて明確な方法論的自覚のもとに論議が行われていたら、果たしてあれ程の紛糾が生じていただろうか。
このように述べた後、碧海教授は、「定義」という論理学上の操作の性格についての本格的な考察を開始する。
その考察についての詳しい論述は、紙幅の関係で割愛せざるを得ないが、「法」を例に採った・「法」の概念規定については、その論理学上の操作の性格は、次のようなものとして解明されることになる。
(1)法の概念規定の問題は、「法」という用語の定義の問題であり、したがって、「法」という用語にどのような対象を指示させることが望ましいか、という問題である。
(2)「法」という用語の定義は、通常多かれ少なかれ不明確にかつ多義的に「法」と呼ばれている対象を認識するのに・最も適した仕方で行われなければならず、その限りにおいて、この種の対象およびそれと類縁関係にある諸種の対象〔道徳や慣習など〕についての経験科学的な研究の成果を十分に考慮した上で、初めてなされなければならない。
(3)「法」の定義は、さらに、この用語の在来の用法を、事情の許す限り、尊重しなければならない。
これが、第二章における最も重要な見解であると言うことができる。
ここでの論述〔(1)、(2)、(3)〕は、説明抜きで概念規定に関する結果のみを記したものなので、理解が困難であると思われるが、碧海教授の著書の第二章を読み十分に理解されるならば、読者の方の思考力は飛躍的に向上することが期待できると、私は考えている。
この第二章「法の概念」は、第三章以降においては、後に述べる第八章「正義の諸問題」(『全訂第二版補正版』では、第七章「正義論の基礎 ―― メタ倫理学の諸問題」が、それに相当する)と並んで、思考方法論の習得および思考力の強化にとって、格好の内容を有するものであると考えられる。
〔20〕 第三章のタイトルは「法の社会的機能」であり、ここでは法というものが社会において果たしている機能を概観している。
この点についての碧海教授の見解を一言で述べるならば、「法」というものを「社会統制のための自覚的技術」として見る立場である、と言うことができる。
この第三章は、『全訂第二版補正版』においては、タイトルが「社会統合と言語」に改められ、内容も刷新されているので、ここでは、以下において、『全訂第一版』の小節のタイトルと『全訂第二版補正版』の小節のタイトルのみを記しておくことにしたい。
『全訂第一版』の小節のタイトルは、以下のようになっている。
一 社会統合、二 社会統制手段としての法、三 近代市民法体制のもとでの社会統制、四 近代市民法体系におけるイデオロギーと現実
『全訂第二版補正版』の小節のタイトルは、以下の如くである。
一 人間における社会統合の特色、二 社会化と社会統制 ―― 統合過程の二側面、三 言語と社会化、四 文明社会における言語と社会統合、五 法による社会統制と言語
第四章の「記号の意味と解釈」では、 ―― 法学においては「解釈」という行為が重要な位置を占めるが ―― 碧海教授は、「我々が『解釈』について的確な論議をするためには、前提条件として『意味』の概念を解明しなければならない。」と述べる。
ここでは、第四章における小節のタイトルを記すことによって、本章がどのようなことを話題にして論じているのかを示すことにしたい。
小節のタイトルを列挙すると、次のようになる。
一 記号体系としての言葉とその社会的機能、二 物神的言語観、三 意味の問題 ―― 記号とその指示機能、四 語の意味と「概念」、五 文の意味と「命題」、六 「明晰さ」をめぐる諸問題
本章の論述は意味論の初歩的内容 ―― 教養として有益な・意味の問題についての最低限の知識 ―― について述べたものであるが、「六 『明晰さ』をめぐる諸問題」など、実際に文章を書く時に大変役立つものとなっている。
第五章のタイトルは「法の適用と解釈」となっているが、この第五章は、『全訂第二版』と『全訂第二版補正版』では、内容が(「法哲学概論」的というよりも)「法学概論」的であるという理由で、全部削除されている。
ここでは、以下に、『全訂第一版』に見られる小節のタイトルのみを記しておくことにする。
一 法源、二 法の適用と解釈、三 解釈の種類 ―― 文理解釈、四 体系的解釈、五 社会学的解釈、六 類推、七 補充的法源の援用(一)(慣習)、八 補充的法源の援用(二)(判例・学説)、九 補充的法源の援用(三)(条理)
第六章「法解釈学の性格と任務」では、まず、この章の目的は、「法解釈学」の名のもとで実際に行われている知的活動とその成果が方法論上どのような性格を持つかを明らかにすることである、と述べられている(「法解釈学」は、憲法学、民法学、刑法学、民事訴訟法学、刑事訴訟法学、等の「実定法学」とほぼ同義である)。
この章についても、本章における小節を記すことによって、本章がどのようなことを話題にして論じているかを示すことにしよう。
一 序説、二 認識の客観性とは何か、三 法解釈学における認識の客観性(一) ―― 論理的・形式的側面、四 法解釈学における認識の客観性(二) ―― 経験的・実質的側面、五 法解釈学における認識と実践、六 法解釈学者と法実務家、七 概念法学と自由法論、八 裁判の準立法的機能、九 結論 ―― 社会統制のための応用科学としての法解釈学
そして、この章での結論を簡潔に記すと、次のようになる。
「科学」を「理論的経験科学」と同義に解すれば、法解釈学は「科学」ではないが、「科学」をもっと広く、「応用科学」をも含むように定義すれば、それは明らかに「科学」と呼ばれる資格を持つ。しかし、それを「科学」と呼ぶ場合にも、それが物理学、生物学、社会学、理論経済学などが科学であるのと同じ意味で科学であるのではない、という点だけは、はっきりさせる必要がある。
法解釈学は、経験的所与としての法の認識をもって能事おわれりとする理論科学ではなく、このような認識に立脚しつつも、さらに自ら実定法の形成・運用に参与する実践的な応用科学である、と考えられる。
第七章は、「法の経験科学」と題されている。「法の経験科学」としては、法社会学、法史学、法人類学などがあるが、『全訂第一版』においては、法社会学と法史学が扱われている。しかし、この章の内容は、むしろ社会科学に重点を置いた経験科学一般についての解説になっていると言える。
本章の各節のタイトルは、次のようになっている。
一 理論と実践、二 マックス・ヴェーバーによる「没価値性」の主張、三 自然科学と社会科学、四 法社会学、五 法史学
特に、一 理論と実践、二 マックス・ヴェーバーによる「没価値性」の主張、三 自然科学と社会科学、の内容は、「ハイレヴェルの教養的知識」としても大変有益である。
次回の掲載は、2025年8月25日の予定です。
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。