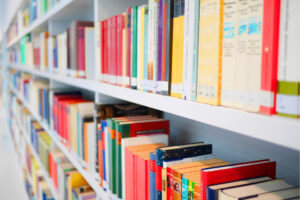私の人格形成に影響を与えた書物と思索 11
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔21〕 「正義の諸問題」と題された第八章では、第二次大戦後の倫理学文献において「メタ倫理学」(「メタ法価値論」は、「メタ倫理学」の一分野とみなされている)と呼ばれる学問領域の問題が考察されている。
「メタ倫理学」のうち「メタ法価値論」に焦点を当てるならば、「メタ法価値論」の分野では、「正・不正の判断のための客観的な規準は、果たして、またどのような形で、存在し得るか」という問題が論ぜられる。
法哲学の歴史は少なくとも紀元前五世紀のギリシャにまで遡ることができるが、古代からほぼ一九世紀に至る法哲学の歴史は、大体において(メタ)法価値論の歴史であった。法哲学には、「(メタ)法価値論」の他に、「法の歴史哲学」および「法学認識論」(「法学方法論」とも呼ばれる)という両分野が存在するが、この両者は、「(メタ)法価値論」よりもはるかに遅く、一八世紀あるいは一九世紀以降に出現したものである。
「正・不正の判断のための客観的規準は、果たして、またどのような形で、存在し得るか」という問題は、哲学気質の人〔物事を深く考え詰めることを好む人〕にとっては、大変興味深い問題であろうと思われる。
『新版 法哲学概論 全訂第一版』の第八章の三「メタ法価値論の諸類型」には、以下のような趣旨の論述がある。
「善」や「正義」についての価値判断の客観性を考察する場合には、この種の価値判断を表す言明と通常の事実言明との比較から出発することが便宜である。「Aは正しい」、「Bは不正である」というような価値言明と、「甲は赤い」、「乙は青い」というような経験的事実に関する言明とを比べた場合、まずはっきりしていることは、両種の言明が、その文法的構造において ―― 日本語でも印欧語でも ―― 全く同一であるということであろう。そこで、問題は、この文法構造上の同一性が、果たして、またどの程度まで、両者間の認識論的同一性または類似性を保証するか、という形で提起され得ることになろう。
この問いに対しては、どのような答えが可能であろうか。
第一の答えは、文法構造上の同一性は「認識論上の同一性に通じ、したがって、価値言明も一種の経験的事実に関する命題であり、真理値〔真とか偽とかいう性質〕を有するものである」という解答である。
第二は、この同一性は「認識論上の同一性は保証しないが、基本的な類似性を示唆し、したがって、価値言明は経験的事実に関するものではないが、やはり一種の客観的事態の存在を主張する命題であり、当然、真理値を有する」という答えである。
第三の答えは、「文法構造上の同一性はむしろミスリーディング〔misleading〕であり、価値言明は、事実言明とは基本的に異種のものであって、何らかの客観的事態の存在の主張ではなく、話者〔スピーカー〕の側の一定の情緒の表現に他ならないものである」というものである。
第一が倫理的自然主義の、第二が倫理的直観〔直覚〕主義の、第三が倫理的価値に関する情緒説(「価値情緒説」または単に「情緒説」とも呼ばれる)の、それぞれ基本的立場を表す。
このうち、第一と第二は、倫理的価値というものを対象に客観的に具〔そな〕わるところの一定の(自然的または「非自然的」)性質と見る点において、客観説に当たり、第三が主観説に当たる、と解される。
客観説に従えば、倫理的価値判断の真偽は原理的に認識可能であるが、主観説は価値判断の認識のみによる正当化は不可能となすものであるから、前者を「認識説」、後者を「非認識説」と称することも可能である。
一方、視点を変えて、「価値判断は事実判断に還元できるか否か」という設問との関連で眺めるならば、自然主義のみが「還元説」となり、直観〔直覚〕主義と情緒説とはともに「非還元説」として分類される。以上の関係を図示すれば、次のようになる。

上の図が示すように、自然主義と価値情緒説とはいろいろな点で相互に対立し、直観〔直覚〕主義はある観点〔「倫理的価値判断の真偽は原理的に認識可能であるか否か」という観点〕からは自然主義に近く、別の観点〔「価値判断は事実判断に還元できるか否か」という観点〕からは価値情緒説に近い。なお、還元説は事実と価値との関係について「事実と価値の一元論」であり、非還元説は「事実と価値の二元論」である、と解することができる。
メタ法価値論上の三つの立場は、それぞれ思想史上の有力な擁護者を持って来た。以下、三者それぞれについて、主張内容とその根拠とを吟味し、その歴史的背景を探ることとしたい。
『新版 法哲学概論 全訂第一版』の第八章の三「メタ法価値論の諸類型」には、上記のような趣旨の論述がある。
このように述べた後、「自然主義」、「直観〔直覚〕主義」、「価値情緒説」に対する本格的な検討が始まる。すなわち、碧海教授はこのように述べた後、第八章の四以下(最後の一〇まで)において、自然主義、直観〔直覚〕主義、価値情緒説のそれぞれの立場について、かなり綿密な考察を行っている。
『新版 法哲学概論 全訂第一版』の内容は、どの章もとても興味深いものであるが、この第八章は、その中でも、興味深い論述内容という点では、「白眉」であると言ってよいと思われる。
そして、私は、前述の第二章「法の概念」のところでも述べたように、読者の方がこの第八章「正義の諸問題」(『全訂第二版補正版』では、第七章「正義論の基礎 ―― メタ倫理学の諸問題」が、それに相当する)を読まれ、その内容を十分に理解されるならば、読者の方の思考力には目を瞠〔みは〕るような著しい向上が期待できる、と確信している。
因みに、碧海教授は、メタ法価値論において、価値情緒説の立場を採っておられる。
私自身も、(メタ法価値論を含む)メタ倫理学をテーマとした『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年)という著書を執筆し出版したことがある。
その著書においては、「善い」という概念の解明〔「善い」とは、一体どういうことなのか、の解明。「『善い』という概念の解明」は、「善い・悪い」〔正・不正〕の判断のための客観的規準は、果たして、またどのような形で、存在し得るか」という問いに対する直接的な解答となっている。〕(第二章および第四章~第六章)や、価値言明の真理性の問題〔価値言明に真理値〔「真」とか「偽」とかいう性質〕を認めることができるか否か、という問題〕(第七章・後半)、「事実と価値の二元論」についての批判すなわち「事実と価値の一元論」が正しいことの説明(「事実と価値の一元論」が正しいか、それとも「事実と価値の二元論」が正しいか、という問題は、社会科学方法論における最重要テーマであり、世界の哲学界および社会科学の世界を巻き込んで論議されてきた「大問題」である。因みに、我が国の社会科学者〔法学者、経済学者、政治学者、等〕の9割以上が「事実と価値の二元論」の支持者であり、哲学者や倫理学者も、大半は「事実と価値の二元論」の擁護者であると言える)(第七章・前半)、価値の内在性についての問題〔ある対象について「善い」と判断する場合、「善い」という価値は対象に内在していると言えるか否か、という問題。例えば、果実が大きくて、赤く、甘くてジューシーなイチゴを「よい」と判断する場合、その「よさ」はそのイチゴに内在している〔含まれている〕か、それともその「よさ」はそのイチゴに対して外在している〔そのイチゴに含まれていない〕のか、という問題〕(第八章・第九節)等の、メタ倫理学に関する根本問題・基本問題が考察され、私の解答が示されている。
その本における私の立場は、基本的に「自然主義」である。
なお、その著書の副題は「≪価値言明の真理性の追究≫のための基礎理論」となっているが、倫理学の最大の課題である「『善い』という概念の解明」について相当数のページを当てて考察されており(第二章および第四章~第六章)、その解答も提示されているので、副題は「『善い』という概念の解明と価値言明の真理性の追究」とする方が適切であった、と今では考えている。
私の意見によれば、「事実と価値の一元論」が正しいか、「事実と価値の二元論」が正しいかは、また、価値言明の真理性の問題〔価値言明に真理値を認めることができるか否か〕は、いずれも「『善い』という概念の解明」に基づいて考察されるべき問題なのである。そうしないと、万人が納得するような十分な合理的説得力を有しないと考えられる。(ただ、「『善い』という概念の解明」を為し得た人は、今までにいなかったように思われる。)
私は、「善い」という語は必ずしも記述的な意味だけを有するものではない(例えば、行為遂行的な面が第一義的である場合もある)と考えているが、私の意見によれば、「善い」という語の(とりわけ記述的な面の)定義は、次のようになる。
すなわち、「対象Aは善い」とは、「対象Aについて与えられた・完全性の程度における極限的な認識意味に対して、 心理写像の結果人間の心に生ずる情緒意味が、 (広義の)心理的意味における『善い』という概念 ―― 『人間にその対象への志向性を促すような・対象の与える情緒意味』の集合 ―― に属する」ということである。
(上記の定義は、『価値判断の構造』の53頁14~16行目と同61頁5~6行目を合成したものである。「認識意味」や「情緒意味」、「心理写像」、「志向性」という言葉の意味については、同書において、わかりやすく説明されている。また、「善い」という語の定義が、どうして上記のような定義になるのかも、同書において、丁寧に説明されている。)
碧海純一教授の『新版 法哲学概論 全訂第一版』の第八章についての論述の最後に、同教授の『全訂第二版』および『全訂第二版補正版』の第七章の三「メタ法価値論の諸類型」について、一言述べておきたいことがある。(先にも述べたように、『全訂第一版』の第八章の内容は、『全訂第二版』および『全訂第二版補正版』では、第七章に移っている。)
同教授の『新版 法哲学概論 全訂第一版』の第八章では特に問題はないのであるが、『全訂第二版』および『全訂第二版補正版』では、第七章の三「メタ法価値論の諸類型」の前半部分が、出版の際の活字の組み方の誤りにより、論述の順序が複雑に前後していて意味がとりづらくなっているのである。このことは、碧海教授の『法哲学概論』が非常にすぐれた学術書であるだけに、大変惜しまれることである。
次回〔最終回〕の掲載は、2025年9月25日の予定です。
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。