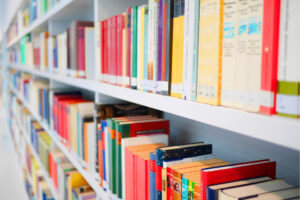私の人格形成に影響を与えた書物と思索 8
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔15〕 さらに、ここで、以下のことも付け加えておきたい。
それは、教養は、「この世界」が蔵する未知の〔自分が今まで知らなかった〕魅力を、 ―― 「この世界」の対象に対して意味づけを行うことによってではなく ―― 直接教えてくれることもある、ということである。
すなわち、その時、教養は、「この世界」における、自分が今まで知らなかった非常に価値ある「世界」(「この世界」が蔵している〔含んでいる〕ものとしての、「世界」)の存在を、直接私たちに教えてくれるのである。
そのような時、私たちは、「この世界」には、こんな魅力的な世界があるのか、と思うことであろう。すなわち、私たちは、「この世界」にもこういう魅力〔魅力的な世界〕が隠されていたのか、と感動するであろう。
そして、私たちは、「この世界」が蔵する・自分が今まで知らなかったその価値を、味わうことになるのである。
例えば、前に引用した露風の「去りゆく五月の詩」の場合、先程、私は、その詩の内容に意味づけされて、「私たちの見ている五月の終わり頃の自然の姿や、それがもたらす情趣」が今までとは変わる、ということを述べた。
けれども、その詩自体が、 ―― 意味づけを通すことなく ―― 直接、私たちの気づかなかった「五月の終わり頃の自然の魅力」 ―― 換言すれば、「この世界」における〔「この世界」が蔵する〕・自分が今まで知らなかった非常に価値ある「世界」(の存在) ―― を教えてくれる、とも言えるのである。すなわち、その詩自体が、直接、「この世界」における・自分が今まで気づかなかった非常に価値ある「世界」(の存在)を、知らせてくれる、とも言い得るのである。
第8番目の勅撰和歌集である『新古今和歌集』(鎌倉時代の初めの、1205年に成立)の中に「三夕〔さんせき〕の歌」というのがある。
『新古今和歌集』の第361番~第363番までの三つの歌で、いずれも「秋の夕暮」で終わる和歌である。(これらの歌は、どれも、三句の終わりが「けり」になっている、という点でも共通している。)
(1) 第361番 「さびしさは その色としも なかりけり 真木〔まき〕立つ山の 秋の夕暮」 (寂蓮法師〔じゃくれんほふし〕)
(さびしさは、とり立てて、秋を象徴する紅葉のようなその色にある、と言うこともできないなあ。常緑樹の檜〔ひのき〕や杉の群れ立つ深山〔みやま〕の秋の夕暮には、どことなくさびしさが漂うよ。)(この歌には、別の解釈もある。)
(2) 第362番 「心なき 身にもあはれは しられけり しぎ立つ沢の 秋の夕暮」 (西行法師)
(喜怒哀楽を超越したはずの私のような出家の身にも、この趣にはしみじみと心打たれるなあ。鴫〔しぎ〕が飛び立つ沢の秋の夕暮の趣には…。)
(3) 第363番 「見わたせば 花ももみぢも なかりけり 浦のとま屋の 秋の夕暮」 (藤原定家朝臣〔ふぢはらのさだいへのあそん〕)
(見渡すと、春の花はもとより、秋の紅葉すら何ひとつないよ。苫葺〔とまぶ〕きの海人〔あま〕〔漁師〕の粗末な小屋が散在する、蕭条〔しょうじょう〕たる海辺の秋の夕暮よ。)
(上記の三つの和歌の表記は、久保田淳校注『新潮日本古典集成 <新装版> 新古今和歌集 上』(2018年、新潮社)に拠っている。後出の第491番も同様。)
因みに、『新古今和歌集』第491番の寂蓮法師の歌は「三夕〔さんせき〕の歌」には数えられないが、やはり五句が「秋の夕暮」となっている和歌である。この歌は『(小倉)百人一首』にも第87番として収められており、私は「三夕の歌」に劣らない秀歌であると思う。
(4) 第491番 「村雨〔むらさめ〕の 露もまだひぬ 真木〔まき〕の葉に 霧たちのぼる 秋の夕暮」
(村雨〔にわか雨〕(「村」はあて字)が通り過ぎた後、杉や檜〔ひのき〕の常緑樹の緑濃い葉の上の露もまだ乾かないうちに、ほの白い霧が立ち昇って、もの寂しい深山〔みやま〕の秋の夕暮となってしまった。)
上に挙げた四つの和歌は、それを初めて読んだ中学生や高校生、あるいは小学生にさえも、(一語で言うならば)「幽玄」の趣を教えるであろう。
彼らは、「この世界」には「幽玄」の趣というものがある、ということを知るのである。すなわち、「この世界が蔵する価値」として、「幽玄」というものがあるということを知るのである。
(「幽玄」という言葉は、時代により、また人によって、意味に幅のある言葉であるが、ここでは、現代における最も標準的な意味であると思われる「美的理念の一つで、言葉に表されない、余情を感じさせる深い趣」という意味に用いている。)
私たちは、上記の四つの和歌によって、「幽玄」の趣を(深く)味わうことができるが、この「幽玄」の趣は、人生において味わうに値する、「この世界」の蔵する(種々の)価値の一つであると言えよう。
これらの和歌(が教える「幽玄」の趣)は、 ―― 私たちは、それによって意味づけをして世界を見るだけでなく ―― それ自体が「この世界の(種々の)価値の一つ」なのである。
幽玄の趣を十分に味わうことができた場合(人生)と、幽玄の趣を全く知らないでこの世を去る〔死去する〕場合(人生)とで、どちらが充実した人生であるかは、あえて言うまでもないであろう。
以上に述べて来た「教養」の働きは、今まで知らなかった「自分にとって新しい価値ある世界を直接知る」ことであって、「私たちの見ている世界を変えてしまう」という働きとは異なるが、それも、けっして逸することのできない「教養」の持つとても重要な意義である、と言える。
そのことによって、私たちは、「この世界」が蔵する・自分が今まで知らなかった価値を味わうことができるのである。
そして、それは、言うまでもなく、私たちの人生を豊かにする。
そのことを、ここに、記しておきたいと思う。
なお、人生に関して述べるためには、私は、「人生とは、唯一回限りのこの世界への招待であり、人生の目的は、この世界が蔵する(種々の)価値を深く味わうことである。」という見解〔人生観〕だけでなく、「生きる焦点」〔人生において自分の生きがいの軸となるもの〕としての「天職」あるいは「自己のライフワーク」の問題にも言及する必要がある、と考えている。けれども紙幅の関係から、ここでは、そのことについては割愛することにしたい。
〔16〕 先程、私は、オスカー・ワイルドの「自然が芸術を真似る」という言葉を説明する際に、伊藤信吉著『現代詩の鑑賞(上巻・下巻)』(新潮文庫、改訂新版、上巻・下巻ともに、1968年)に収められている三木露風の「去りゆく五月の詩」を引用した。
この『現代詩の鑑賞(上巻・下巻)』には、北原白秋や高村光太郎、萩原朔太郎、草野心平、西脇順三郎ら、明治から昭和30年頃までの21人の代表的な詩人の計250編(上巻11人、130編、下巻10人、120編)の詩が収録されている。そして、250編の各詩には、伊藤信吉〔しんきち〕氏(1906~2002年)の大変すぐれた鑑賞・解説文が記されている。
私は、この本によって、詩のすばらしさ、詩の魅力を知った。
伊藤信吉氏は、詩は私たちの生活と精神とにおける一つの結晶作用である、と言う。詩人は、その結晶作用を圧縮された一瞬の時間のうちに捉え、それを一定の様式をもって言葉に定着させる。あるものは炎のように燃えて人の思いを灼〔や〕き、あるものは氷のように冷たく人の思いにしみ入る。伊藤信吉氏は、このように述べる。
私は、そのとおりであると思う。
また、『現代詩の鑑賞(上巻)』の「序」のすぐ後に置かれた「引用詩について」では、「本書[上巻]に引用した詩は全部で百三十篇を数えるが、これらの詩は各詩人の代表的作品といってよく、明治・大正年代におけるすぐれた文学作品ということができる。したがって、百三十篇は、おのずから明治・大正代表詩集を成すわけで、下巻の引用詩とともに、これは現代詩の成果を集約したものである。」と記されている。
絵画が「形と色の芸術」であり、音楽が「音の芸術」であるように、詩は「言葉の芸術」である。
私は、伊藤信吉氏の『現代詩の鑑賞(上巻・下巻)』は、日本の近・現代詩の分野における至宝であると思う。文章も読みやすく、理解・納得しやすいものである。
私は、この『現代詩の鑑賞(上巻・下巻)』を読むことによって、自分の美的センスが以前に比べれば少なからず向上したのではないかと思っている。
この本に収録されている詩や、それに付されている伊藤氏の鑑賞文は、私たちの審美眼や美意識の養成に十分に資するものであると思う。
伊藤信吉氏は日本現代詩人会会長や萩原朔太郎研究会会長などを歴任されているが、『現代日本詩人全集(全16巻)』(東京創元社、1953~1955年)の全巻の解説も担当された。また、1964年版の平凡社の『世界大百科事典』において、「日本の詩」の項目の執筆も担当されている。より新しい版の同『世界大百科事典』においては、大岡信氏が「日本の詩」の項目を執筆されているが、私は、どちらかと言うと、伊藤氏の執筆された「日本の詩」の項目の文章の方に、より愛着がある。
『現代詩の鑑賞(上巻・下巻)』は私の座右の書の一つであり、私は、伊藤氏を、「自分の情緒面における恩師」であると考えている。(因みに、伊藤信吉氏の学歴は、大卒ではなく、高等小学校卒である。当時は、修学年数は、尋常小学校が6年、その上の高等小学校が2年であった。)
私は、この『現代詩の鑑賞(上巻・下巻)』の中で、三木露風の「去りゆく五月の詩」の他、同「現身〔うつせみ〕」(先にも述べたように、露風の全業績を代表するものの一つ。エレガンスの抒情を表現した詩として、「現身」は最高の作品であると言われる。)、蒲原有明〔かんばらありあけ〕の「茉莉花〔まつりか〕」(茉莉花は、白い花に強い芳香のあるモクセイ科の常緑低木。観賞用に鉢植えとして室内に置かれることも多い。この詩は有明の詩における最高の作品とされ、フランス近代詩のすぐれた作品にも劣らないと言われる。)、北原白秋の「謀反〔むほん〕」(白秋の第一詩集『邪宗門』(1909年刊)を代表する作品の一つで、ヴァイオリンの変化する音色に導かれながら、それによって、哀愁、熱気、頽廃といった情緒の変化をたどってゆく手法を採った象徴詩である。この作品は、詩人の蒲原有明が絶賛し、詩人で英文学者の日夏耿之介〔ひなつこうのすけ〕が酷評したことでも知られる。)、同「曇日〔くもりび〕」、同「風のあと 断章六十六」、高村光太郎の「雨にうたるるカテドラル」(「ノートルダム ド パリのカテドラル」をうたったこの詩は、高村光太郎が生涯に発表した全729篇の作品において、その最高峰に位置する詩であるばかりでなく、日本の近代詩全体の展望から言っても、記念碑的作品である。全篇105行にわたるこの詩は、引いてはまた押し寄せる波のうねりのような音楽性を有し、すぐれた交響曲を聴いた時のような感銘を、読む者に与える。高村光太郎は詩人であるとともに彫刻家でもあったが、これは、彫刻家としての感動が、詩人の最も熱い言葉でうたわれた作品である、と言える。)、同「レモン哀歌」、萩原朔太郎の「悲しい月夜」、同「さびしい人格」(萩原朔太郎の第一詩集『月に吠える』(1917年刊)に収められている詩である。「さびしい人格」は、上記の詩集において、精神的孤独の感情を独自の抒情にまで成熟させた朔太郎の詩の魅力を、十分に味わうことのできる作品である。)、同「青樹の梢をあふぎて」、同「黒い風琴〔ふうきん=オルガン〕」、同「群衆の中を求めて歩く」、中野重治の「雨の降る品川駅」、草野心平の「富士山(第肆〔し〕)」、同「聾〔つんぼ〕のるりる」、西脇順三郎の「皿」、同「旅人かへらず 一」(因みに、「皿」が収録されている西脇順三郎の第二詩集『Ambarvalia〔アムバルヴァリア〕』(ラテン語で、古代ローマの農業神、ケレスを祀る儀式(したがって、穀物祭)の意。)(1933年刊)と、「旅人かへらず 一」が収められている第三詩集『旅人かへらず』(1947年刊)は、その詩風または詩的情操において、著しい相違がある。前者は、南欧風の情趣が感じられる明るく美しい詩風であるのに対して、後者は、人生の果てに行き暮れたような寂寥感の漂う詩風である。彼の詩集『旅人かへらず』には、ほとんど断章と言ってもよいほど形の小さい作品も多く、計百六十八篇が収められているが、それらは、彼が「玄〔げん〕の世界」あるいは「玄〔げん〕の精神」と呼ぶ境地にまで詩境が深められたものであり、極めて味わいの深いものである。因みに、西脇順三郎の第一詩集は、1925年にロンドンで刊行された『Spectrum』と題する英文の詩集である。)などの詩が、特に印象深い。
また、この本には収録されていないが、北原白秋の「室内庭園」(詩集『邪宗門』において、巻頭の(「百年〔ももとせ〕を刹那〔せつな〕に縮め、血の磔背〔はりきせ〕にし死すとも惜〔を〕しからじ、 願うは極秘、かの奇〔く〕しき紅〔くれなゐ〕の夢」とうたう)「邪宗門秘曲」のすぐ後に置かれている詩。「室内庭園」は、白秋の詩の中では、私の最も好きな作品である。この詩は、集中の最高傑作であると思う。)、「空に真赤な」や木下杢太郎〔もくたろう〕の「緑金暮春調」(この作品は、憂愁と甘美が融け合うような・晩春の黄昏時〔たそがれどき〕の情緒をうたった詩である。「緑金暮春調」の「緑金」は、この詩の第一節の「その[噴水の]律〔しらべ〕やや濁〔にご〕り、緑金〔りょくきん〕の水沫〔しぶき〕かをれば、」から採ったものと思われる。因みに、木下杢太郎(1885~1945年、本名:太田正雄)は、東大医学部教授等(皮膚科学)を歴任した医師でもあった。)、高村光太郎の「樹下の二人」、草野心平の「桃」(『絶景』所収)(草野心平(1903~1988年)のこの「桃」は、『草野心平詩集』(岩波文庫)にも、『草野心平詩集』(新潮文庫)にも収められていないが、私はこの詩は非常にすぐれた詩であると思う。私は、この詩を『日本の詩歌 21』(中公文庫)で知った。因みに、この詩は「桃」を主題にした詩ではなく、広い意味での「青春の心境」を歌った詩である。1987年の秋に、私が自宅の茶の間でこたつに入ってテレビを見ていた時、NHKのニュースで、草野心平が文化勲章を受章した旨が伝えられた。その時、私と一緒にテレビを見ていた父が、(受章するのが)「遅すぎたよ。」と一言ぽつりと言ったのが、今でも印象に残っている。草野心平は、翌年の1988年に病没した。他の詩もそうであるが、この詩〔「桃」〕を読むと、私は「草野心平は詩人だなあ。」とつくづく思う。)などの詩も、とても好きである。
次回の掲載は、2025年6月20日の予定です。
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。