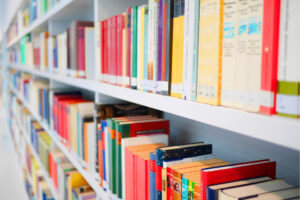私の人格形成に影響を与えた書物と思索 12〔最終回〕
小林 誠(こばやし・まこと)
著述業・哲学研究者
私の人格形成に影響を与えた書物と思索
〔22〕 碧海純一著『新版 法哲学概論 全訂第一版』に関する論述の最後に、碧海純一先生と私との親交〔お付き合い〕について、簡単に記しておくことにしたい。
私が碧海先生とお付き合いさせていただくようになったのは、1990年に私が先生に自分のメタ倫理学関係の論文をお送りして、それをお読みいただいたことに始まる。
先生のお計らいで、翌1991年の5月に、東京都文京区本郷の学士会館分館において先生とお会いして、私の論文の内容に関して3時間余り先生とお話しする機会を持った。私の論文は、上に述べたようにメタ倫理学に関するものであったが、先生はメタ倫理学について価値情緒説の立場を採っておられ、私は自然主義の立場を採っていた。しかし、先生と私とでメタ倫理学上の学説が対立していたにもかかわらず、先生は私の論文を非常に高く評価してくださった。
その後、私は、上記の論文を増補改訂して、『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年)という著書として刊行した。
先生にも一冊お送りさせていただいたが、まもなく先生からお電話がかかって来て、先生は、「メタ倫理学において、私は長い間ずっと価値情緒説が正しいと思って来ましたが、あなたが送ってくれた本を読んで、やっぱりあなたの言う自然主義の方が正しいのではないかと思いました。」と言われた。(私の採っている自然主義の方が本当に正しいかどうかは別論として、)先生は、私の立場の方が正しいかもしれないと思われると、率直にそのことを表明して賞賛することを惜しまれない方であった。先生は、後日、私のその著書についての感想を記したご書面も私にお送りくださった。
私は、最近、『「存在」という概念の解明』という著書も出版したが ―― その著書では、「『存在』とは何か」、すなわち「『存在する』という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか」という哲学の根本問題が扱われている ―― 、先生にその初期の草稿をお読みいただいた時にも、先生は、「存在の問題はアリストテレスもカントもラッセルも重要視した哲学の根本問題ですが、……その解決のために、実に驚くべく独創的な分析を試みてい〔る。〕」と記したお手紙(1999年9月30日付)を私に送って来てくださり、私を励ましてくださった。
大変僭越ながら、私の意見を率直に記すことが許されるならば、私は、『「存在」という概念の解明』という著書において、古代ギリシャ以来現在に至るまで、二千数百年間未解決であり続けた上記の難問が「基本的には解けている」のではないかと考えているのであるが、如何であろうか。
読者の方に、その「ご判定」のために、本書〔『「存在」という概念の解明』〕をお読み頂ければ、光栄である。
因みに、世界の哲学界において大勢を占める見解は、「『存在する』という概念は、複合概念ではなく、単純概念であって、これ以上分析はできない。」、そして「『「存在する」という概念がどういう概念かを解明〔説明〕せよ。』と言われても、それは説明できない、説明のしようがない。」、というものである。(なお、カントは、「存在」という概念を、認識主観が行う「定立〔Position〕」という言葉を用いて説明しようとしているが、 ―― 私の意見と異なり ―― 「存在する」は「事象内容を表す述語〔reales Prädikat〕」ではない、としている。(『純粋理性批判』の歴代のほとんどの訳者は、reales Prädikatを「実在的(な)述語」と訳されているが、この訳語は不適当であると思われる。その説明〔理由〕については、本書の275~277頁の註(3)に記されている。))
私は、上記の見解に反対して、「存在する」という概念は複合概念であり、分析可能であるとして、本書の第二章や(「はしがき」の後の)「本書の結論的見解」において、同概念を解明〔説明〕して見せたものである。
私の意見によれば、例えばAが一般名辞である場合、
「A(例えば、カモシカ)が存在する」とは、「ある適当な認識水準において『A(カモシカ)』という言葉によって指示されうるある対象〔認識対象〕が、認識水準の極限からそれを見ても、A(カモシカ)としての同一性を保持する」ということである。
換言すれば、「A(例えば、カモシカ)が存在する」とは、「ある適当な認識水準において『A(カモシカ)』という言葉によって指示されうるある対象〔認識対象〕が、認識水準の極限において、(認識主観の)認識の対象になり得る」ということである。
私の考えによれば、これが、古代ギリシャ以来二千数百年間にわたって探究されて来た「存在」の正体なのである。
(上記の解明〔分析〕における「一般名辞」や「認識対象」、「認識水準」という言葉の意味は、本書において、丁寧に説明されている。)
「『存在』という概念の解明」という問題が解決できると、その解明結果に基づいて、「存在」概念に関する実に多くの未解決の問題を(一挙に)解くことができるのである。
(『「存在」という概念の解明』という本は比較的厚い本ではあるが、「『存在』という概念の解明」の問題についての「私の解答」を知るためならば、本書の総論部分である第二章~第一三章まで(約110ページ)を読まれれば、十分である。また、本書には、読者の方の便宜のために、「はしがき」の後に、「本書の結論的見解」と題して、「本書における私の重要な見解」が25個箇条書で明記されている。なお、この著書は、大学図書館や公立図書館に置かれていると思われる。)
私には、もちろん研究者として欠点や至らぬ点があったが、碧海先生はそのような点には触れず、少なくとも私に関しては、「褒めて育てる」という態度で接してくださったように思われる。
なお、私は、先生から学問的に非常に多くのことを学ばせていただいた他、先生ご夫妻にご媒酌の労をとっていただくなど私的にもお世話になった。
私は先生と学問的見解がすべて一致しているというわけではないが、そのような相違を超えて、先生は私の最も敬愛する恩師であった。
そして、この著書(『新版 法哲学概論 全訂第一版』、最新版は『全訂第二版補正版』)も、そのような相違を超えて、大変すばらしい本であると、私は思っている。この著書には、著者の高い知的エートスが全編から滲み出ている。
碧海純一先生の『法哲学概論』(前述のように、最新版は『新版 法哲学概論 全訂第二版補正版』)は、二十世紀後半(からおそらく現在に至るまで)の我が国において望みうる最高の「法哲学の概説書」であるとともに、同時に、「思考方法論」〔ものの考え方〕を学び思考力を強化・向上させるための絶好の「教養書」でもある。そして、その文章は、 ―― 戦前の日本の哲学書によく見られるような難解晦渋な文体ではなく ―― 極めて明晰でわかりやすい文章なのである。
私は、若い方々を初めとする江湖に、この名著を読まれることを、改めて広く推奨したいと思う。
〔23〕 私は、これまで、(1)「しあわせの島」、(2)『いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ』、(3)『力の算数5000題』、(4)『現代詩の鑑賞(上巻・下巻)』、(5)『新版 法哲学概論 全訂第一版』という自分の人格形成に大きな役割を果たした五つの書物や物語のことを軸として、また私自身の思索内容も織り交ぜながら、文章を綴って来た。
私自身が哲学に携わる身であるため、綴って来た文章の内容が少なからず哲学色の濃いものになったように思われる。
物事を深く考え詰めることを好む人にとっては、その内容に興味を持たれた方もおられると思われるのであるが、そうでない方には、関心の持てない内容になってしまったのではないかと恐れている。
ただ私としては、全く手を抜くことなく、あくまで誠意を込めて文章を書いて来たのであり、その点はご理解いただければ有難い次第である。
ここに記した文章の内容が、読者の方にとって、今後の人生において何らかの役に立つならば、望外の幸せである。
また、この「40周年記念コラム」をお読みくださった方は、多少なりとも私との接点〔関係〕を持ってくださった方であるが、そのご縁から、読者の方には、納得できる幸福な人生を送られることをお祈り致したく思う。
最後に、私にこのような場を与えてくださった玉田勝博社長に感謝申し上げるとともに、改めて貴社の設立四十周年を祝して、将来における一層のご盛栄を心よりお祈り申し上げる次第である。
(完)
◎ 長らくご愛読いただき、有難うございました。
小 林 誠
略歴
小林 誠(こばやし・まこと)
| 1958年 | 埼玉県に生まれる。 |
| 慶應義塾大学経済学部卒 | |
| 現 在 | 著述業 哲学研究者 日本哲学会、日本科学哲学会、日本法哲学会、会員 (日本哲学会については、元日本哲学会会長の沢田允茂先生が拙著『価値判断の構造』について、「博士の学位論文に十分になり得る。」と言ってくださり、同学会に入会したものである。) |
| 専 攻 | 哲学(哲学的価値論、存在論、意味論) |
| 著 書 | 『価値判断の構造』(恒星社厚生閣、1998年) (価値についての理論的問題の双璧とも言える、「善い」という概念の解明と価値言明の真理性の問題を主たるテーマとし、基本的に自然主義の立場に立つ自分の解答を提示した、メタ倫理学に関する体系的モノグラフィー) この『価値判断の構造』は、人事院の作成する平成30年の国家公務員試験〔大卒・総合職〕(旧国家公務員上級試験)の試験問題に採用された。 『「存在」という概念の解明 ― 新しい存在論原理の展開』(北樹出版、2021年) (「『存在』という概念の解明」〔「存在する」という言葉によって、私たちは一体何を言おうとしているのか、の解明〕という、古代ギリシャ以来二千数百年間未解決であり続けた難問の解決を試みた著書) |
無断複写・転写を禁じます
たとえ一部分であっても、本文章の内容の転載や口頭発表等は、ご遠慮ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。